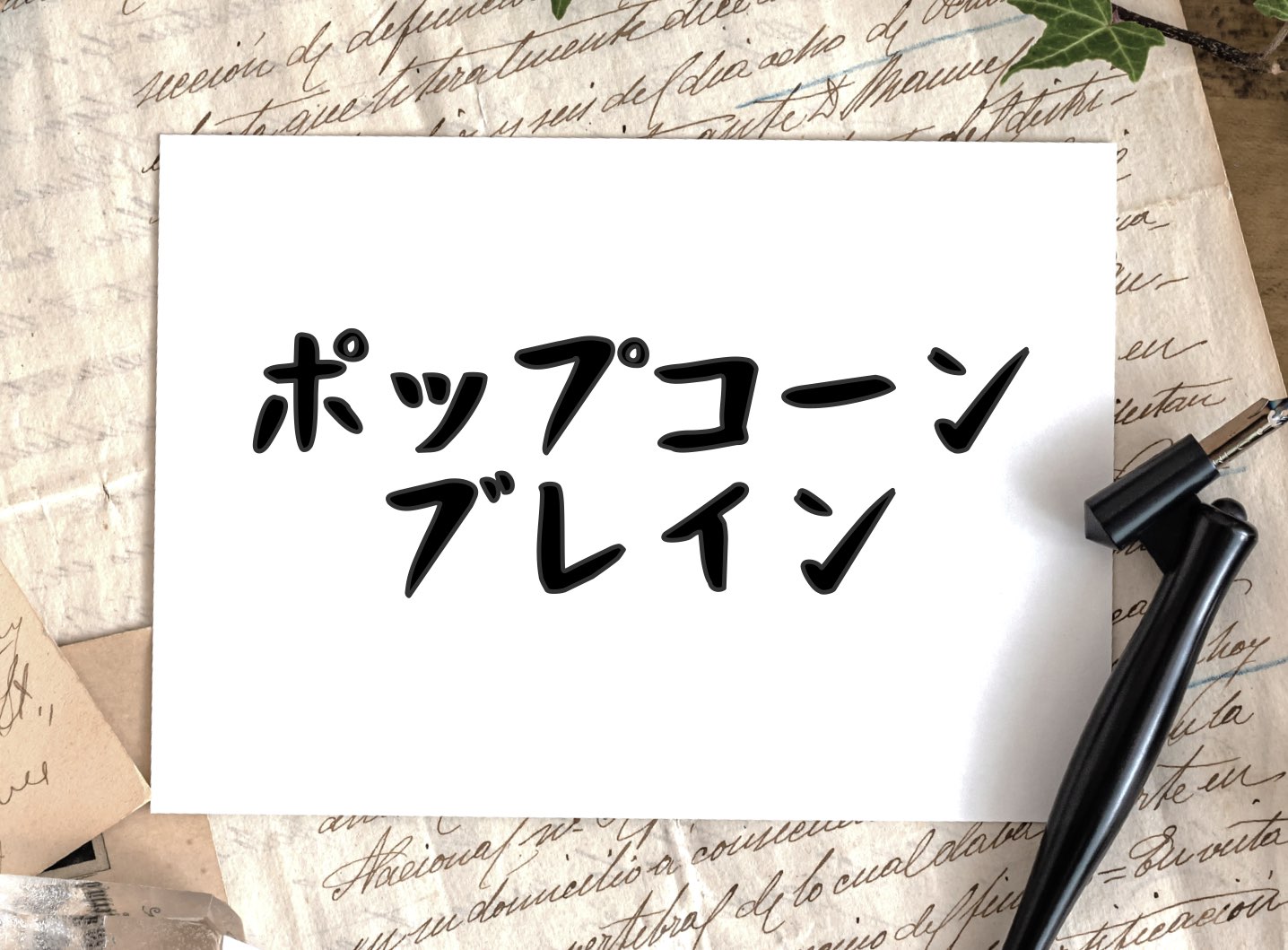コーピング
今日はストレスに対処するための行動であるコーピングについてお話してみようと思います。copeとは英語で対処する・乗り越える、という意味があります。

コーピング理論とは
アメリカの心理学者リチャード・ラザルスとスーザン・フォークマンによって提唱されました。ストレスとは主観的なもので、 同じ出来事でも人によって「ストレス」と感じるかどうかは異なります。
ストレスには、これは自分にとって脅威か?自分には対処手段があるか?、という認知評価が重要とのことです。
コーピングの種類
コーピングには2種類があるようです。
・問題焦点型コーピング・・・問題の解決を試みる
例えば仕事が多すぎることでストレス過多になっている。それに対して、上司と相談して仕事量を調整することを試みる。
このように解決できそうな問題課題に対して積極的にアプローチすることを問題焦点型コーピングといいます。
・情動焦点型コーピング ・・・感情を落ち着けようとする
例えば、深呼吸・気分転換など、抱えているストレス自体を発散させる。
根本解決が難しい問題課題に対しては、ストレスそのものにアプローチすることを情動焦点型コーピングといいます。
コーピングの実験・研究
【研究1】大学生の試験ストレス
大学生を対象に、期末試験におけるストレス体験とコーピング行動を日記形式で記録してもらいました。
その結果、成績を上げようとする学生は「問題焦点型コーピング」を多く用いたようです。ただ試験後は「情動焦点型コーピング」(気晴らしなど)が増えたとのこと。
このことから、ストレスの局面によって使われるコーピングが変化することがわかりました。
【研究2】看護師のバーンアウト研究
病院勤務の看護師を対象にアンケートによるストレス要因とコーピング戦略の分析をしました。
その結果、感情的なサポートを得ている看護師ほどバーンアウトしにくく、問題を回避する傾向が多い人はメンタルが悪化しやすいことが分かりました。
【研究3】日本のビジネスマンとコーピング
日本の企業におけるストレスマネジメント調査をすることで、「我慢」や「責任感」による内的抑制が多い事が分かりました。欧米に比べ、飲みに行って愚痴を言い合うなど「情動焦点型」が多用される傾向にあるようです。
【実験例】スピーチ課題を使ったストレス実験
学生を2グループに分け「突然スピーチさせる」状況を作り、心拍数やコーピング戦略を測定しました。
・グループA:事前に問題焦点型の対処(準備やリハーサル)を指導
・グループB:情動焦点型(呼吸法、前向き思考)を指導
その結果、両方ともストレス軽減に効果があったものの「長期的な自信や成長感」はAの方が高いことがわりました。やはり根本的な問題解決が長期的なメンタルの安定につながるということですね。
終わりに
この記事を書きながら、ここ最近ストレスについての話題が多いような気がしていましたが、私は元気です。強いて言うなら夏が近づいてきて私の最大の宿敵「虫さん」が増えてくることを懸念していることでしょうか。これに対して、問題焦点型コーピングは機能しにくいため、情動焦点型コーピングを実行するほかありません。対処行動療法などを行うことで問題焦点型コーピングにアプローチを行うことも出来そうですが、その過程で人格破綻しそうなので止めておこうと思います。頭打ったおかげで、虫さん好きになりたい!と七夕に何度お願いしようとしたことか。
そうですね、お願いするなら「今年の夏も乗り越えられますように」くらいにしておきましょうか。(何の話なんでしょうか)
さて、全く関係ないのですが、
上司の性格によって、部下のコーピングスタイルが変わるらしい。
男性スタッフの越智でした。
@余計な一言@
支援的で柔軟な上司だと部下は問題焦点型コーピングをとりやすいそうですよ。
*****************************************************************************
フィールHP
https://www.feel-inc.net/
お問合せフォームよりご連絡ください
*****************************************************************************
株式会社 フィールは、ブライダル事業と研修事業を行っている会社です。
司会のこと
結婚式場紹介やプロデュースのこと
婚活のこと
企業研修のこと
フィールがお手伝いできることきっとあります。
お気軽にご相談くださいませ。
☆司会者募集中☆
お問合せフォームよりご連絡ください
******************************************************************************