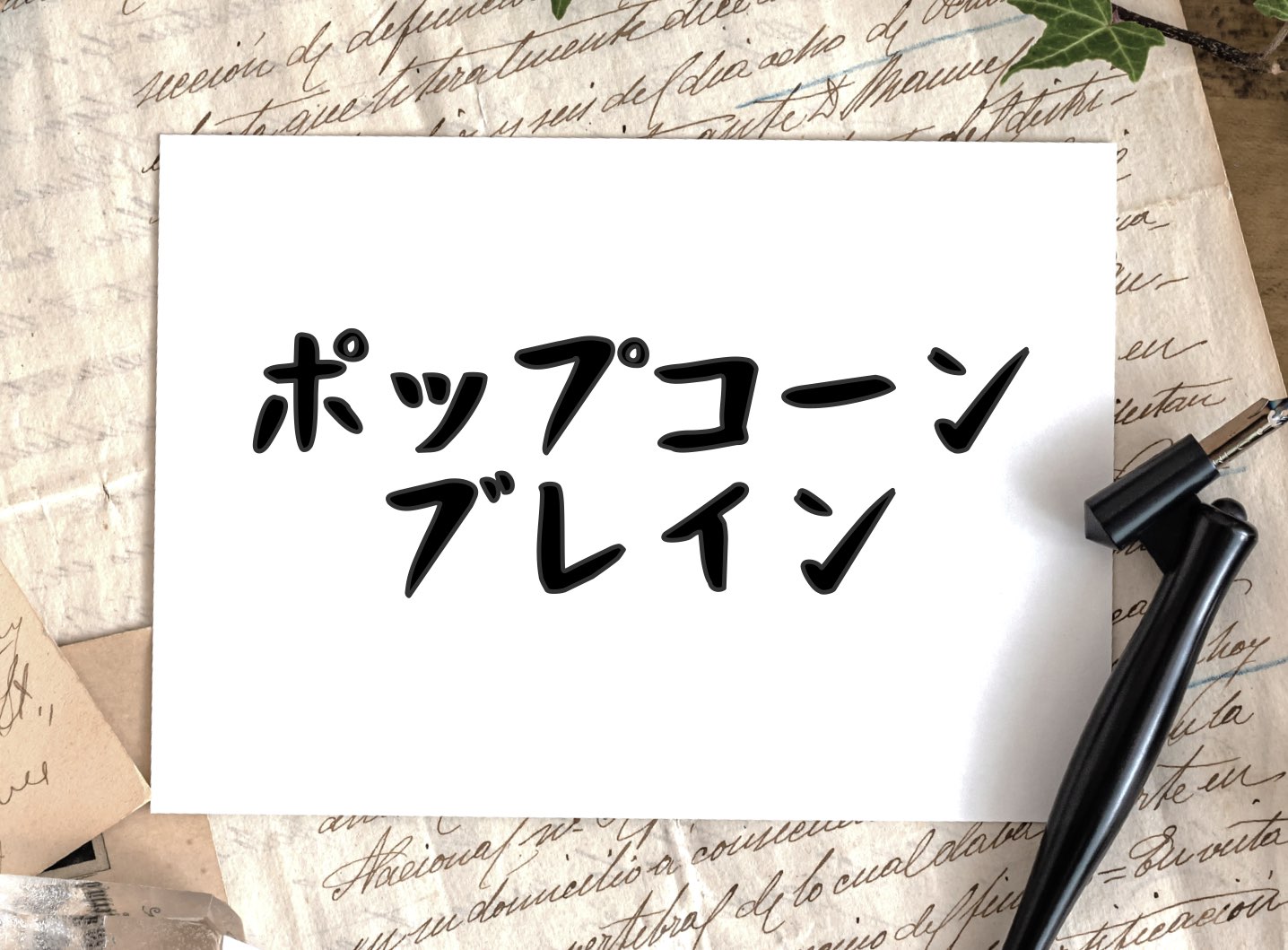強制された勉強
今日は学生時代に強制的にやらされた勉強には意味があるのか、についてお話ししてみようと思います。
子育てで勉強嫌いな子にさせる勉強の参考になりそうですし、お仕事で、やる気のない人に任せる業務はどんなものが良いか、の参考にもなるかもしれません。

強制でも効果がある勉強
これは「機械的な反復練習が効果を持つ分野」で、パターン化出来るモノや暗記物が対応します。
○読み書き(識字能力)
ひらがな、カタカナ、漢字の読み書き、アルファベットの基礎などは、毎日の反復で必ずある程度はできるようになります。
Stanovich (1986) は「読みのスキルは練習量と環境によってほぼ全員が習得可能」と指摘しています。義務教育での反復練習により、基本的なリテラシーは強制的に習得できることが示されています。
•研究名: Matthew Effects in Reading
•概要: 「読書力の格差は小さい頃の反復練習量で大きく開く」ことを示した。読みの基礎(文字認識・音読)は反復で全員がある程度習得可能だが、語彙や理解力は差が広がる。
•結論: 強制練習で「読む」こと自体はできるようになるが、深い理解には自主的な読書経験が必要。
○基礎計算(算数の四則演算)
掛け算、九九や簡単な割り算、分数の計算などは、反復練習によって「自動化」されるので、強制的な学習でも習得率が高いです。
Ashcraft (1992) は「基礎計算は反復練習で長期記憶に固定され、自動化される」と報告しています。九九や四則演算は強制反復で誰でもある程度習得可能とのこと。
•研究名: Cognitive Arithmetic: A Review of Data and Theory
•概要: 計算能力は「反復による記憶化」と「概念理解」の二段階があると分析。九九や四則演算は反復で「自動化」され、ほぼ全員が習得可能。
•結論: 強制練習で「計算スピード・正確さ」は伸ばせる。
米国の研究(Rathvon, 2004)では、毎日短時間の計算練習を義務的にさせると、ほぼ全員の計算スピードが向上することが示されたようです。
•著書: Early Reading Assessment: A Practitioner’s Handbook
•概要:「毎日短時間の計算ドリル」を小学生に課すと、計算スピードと正答率が向上することを実践的に示した。
○音読・暗記系
歴史の年号、簡単な理科用語、英単語の基礎などは「丸暗記」でもある程度身につきます。
National Reading Panel (2000、アメリカ議会報告書) のメタ分析では、音読や反復読書を強制的に行わせることで「単語認識スピード」「文章理解力」が向上することが確認されています。
•調査範囲: 1966〜2000年の400以上の研究をレビュー。
•結果:「音読練習(Repeated Reading)」は読解速度・単語認識を大幅に改善。基礎リテラシーの強制学習の有効性を実証。
強制だけでは難しい勉強
一方で、「考える力」や「応用」が必要な学習は、強制だけでは効果が薄くなります。
○文章読解力
文字は読めても、内容を理解する「読解力」は強制だけでは身につきにくいらしい。背景知識や興味、対話的な学びが不可欠とのこと。
これについて各国で「文字は読めるが内容を理解できない“機能的非識字”」が問題になっています。日本でもごんぎつねが読めない子どもたちが話題になってましたね。
強制的に文字を読ませても、理解力や批判的思考は伸びにくいことが分かっています。
○数学の応用(文章題や証明など)
計算のように「型」がないので、強制だけでは理解できない子が多くなります。
Hiebert & Grouws (2007) は「計算スキルの練習は自動化に有効だが、応用問題の解決には概念的理解が必要」と指摘。強制だけでは「なぜそうなるか」を理解する学びにはつながりにくいとされます。
•研究名: The Effects of Classroom Mathematics Teaching on Students’ Learning
•概要: 教室での数学教育を調査。計算の反復はスキル習得に効果的だが、文章題や応用問題の理解には「概念的な説明・対話」が必要。
•結論: 強制練習だけでは「応用力」は伸びない。
○英語の会話・表現
強制的に単語や文法を覚えても、実際に「自分の考えを英語で表す」力は鍛えにくいです。
Krashen の「インプット仮説」(1985) によると、単語暗記や文法練習(強制学習)だけでは「使える言語能力」にはならず、理解可能なインプットやアウトプットの場が不可欠
•研究名: The Input Hypothesis
•概要: 言語習得は「理解可能なインプット」を通じて起こる。文法暗記や強制反復では「話せる力」にはならない。
•結論: 単語・文法暗記(強制学習)は可能だが、運用力には実際の使用経験が必要。
○理科・社会の概念理解
「なぜそうなるか?」を考える部分は、丸暗記では限界があります。
・理科、探究学習についてHmelo-Silver, Duncan & Chinn (2007)
•研究名: Scaffolding and Achievement in Problem-Based and Inquiry Learning
•概要: 探究型学習(Inquiry-Based Learning)のメタ分析。知識定着は従来型授業と大差ないが、概念理解・問題解決力は大幅に向上。
•結論: 強制暗記より「問いを立てる学び」が応用力を育てる。
社会(歴史・公民)についてOECD PISA 調査 (2000〜継続)
•概要: 世界各国の15歳を対象に読解力・数学・科学的リテラシーを測定。
•結果:「文字は読めるが意味を理解できない」=機能的非識字が日本含む多国で確認。
•結論: 年号や用語の暗記(強制学習)は習得できても、因果理解や批判的読解は伸びにくい。
終わりに
強制的な勉強によって習得しやすいのは、パターン化されるもの・暗記物・音読、という感じでしょうか。強制的に勉強をがんばってもらって、この3種類を身につけておけば、将来自主的に勉強するようになったとき、相当役に立ちそうですね。
読解力についても問題視されることが多く、映像コンテンツの普及も原因の一つであると聞いたことがあります。自分で理解しなくても、映像が勝手に説明してくれてどんどん先に進めていってしまい結論に辿り着くから、考えることをせずに問題と結論が結びついてしまう〜みたいな考察をみて、なるほどなーと思いました。
世代間のギャップは確実に存在するので上手に対応出来るようになっておきたい、、、と日々思います。
さて、全く関係ないのですが、
頼みごとは右耳に話しかけるといいらしい。
男性スタッフの越智でした。
@余計な一言@
成功率2倍らしいし、右耳から聞いた方が理解しやすいらしい。
*****************************************************************************
フィールHP
https://www.feel-inc.net/
お問合せフォームよりご連絡ください
*****************************************************************************
株式会社 フィールは、ブライダル事業と研修事業を行っている会社です。
司会のこと
結婚式場紹介やプロデュースのこと
婚活のこと
企業研修のこと
フィールがお手伝いできることきっとあります。
お気軽にご相談くださいませ。
☆司会者募集中☆
お問合せフォームよりご連絡ください
******************************************************************************